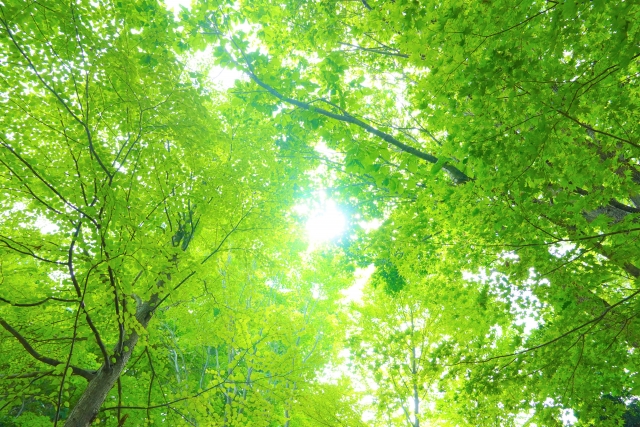相続– category –
-

相続登記義務化の運用方針
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます(改正不動産登記法第76条の2)が、2023年3月22日に法務省サイトにて義務化施行の運用方針が公表されています。 相続登記は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したこと... -

胎児の相続権
人の権利能力は出生により生じる(民法第3条1項)ため、まだ生まれていない胎児には基本的に権利能力がありませんが、相続権については例外的に認められています(民法第886条1項)。 例えば、Aの妻Bに胎児CがいたがAが亡くなった場合、仮に胎児に相続権が... -

相続財産法人への氏名変更登記
亡くなった方に相続人がいない場合など「相続人のあることが明らかでないとき」は、被相続人が所有していた財産は法人として取り扱われます(民法第951条)。 通常亡くなった方の所有財産は相続人に承継されることになりますが(民法第896条本文)、元々相... -

ゆうちょ銀行の相続手続
ゆうちょ銀行の口座名義人が亡くなった場合の相続手続(2022年12月時点)は、下記の通りです。 ①相続関係や口座の記号番号などを記載した「相続確認表」をゆうちょ銀行(郵便局)の窓口に提出します。他の銀行と異なり、支店の指定があるわけではないため... -

AI-OCRによる手書き文字の自動解読
凸版印刷株式会社が明治期から昭和初期の手書き文字を自動解読できるシステム(AI-OCR)を開発し、2023年4月にサービス開始予定です(凸版印刷株式会社公式WEBサイトより引用)。 2024年4月1日より相続登記の義務化が始まりますが、相続登記手続きにおいて... -

配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続財産である居住建物に、被相続人死亡後も引き続き無償で住み続けることができる権利です(民法第1028条1項)。配偶者居住権の設定には、遺産分割や遺言が必要となります。 例えば、被相続人Aの配偶者B(子Cがいる... -

配偶者の相続税の税額軽減特例
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に相続財産を取得した場合、①1億6,000万円、又は②配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい金額までは、相続税はかかりません。 そのため、例えば相続財産額が1億6,000万円である場合、全て配偶者に相続させる... -

遺産の一部分割
遺産の一部分割とは、遺産全てについてまとめて分割協議を行うのではなく、遺産の一部について先に遺産分割を行うことです(民法第907条参照)。 遺産分割は、遺産全てにまとめて行うことが通常ですが、遺産が多岐にわたるため話し合いに時間がかかりそう... -

代償分割
代償分割とは、遺産分割方法の一つで、ある相続人がある相続財産を取得する代わりに(代償として)、その相続人から他の相続人に対して金銭などを支払うことを約することをいいます。 相続財産が全て金銭(預貯金)のみの場合には、遺産分割において財産を... -

遺留分の放棄
遺留分(民法第1042条)とは、被相続人の遺言においても侵害されない最低限の相続できる割合のことです。相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)が、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の手続を要せず自由に行うことがで...